

コーチングセッションのなかでのセッションの展開に大きく関わってくるのがコーチによる『質問』です。
コーチングにおける『質問』は普段の会話でおこなうような質問とは意味や方向性が異なってきます。
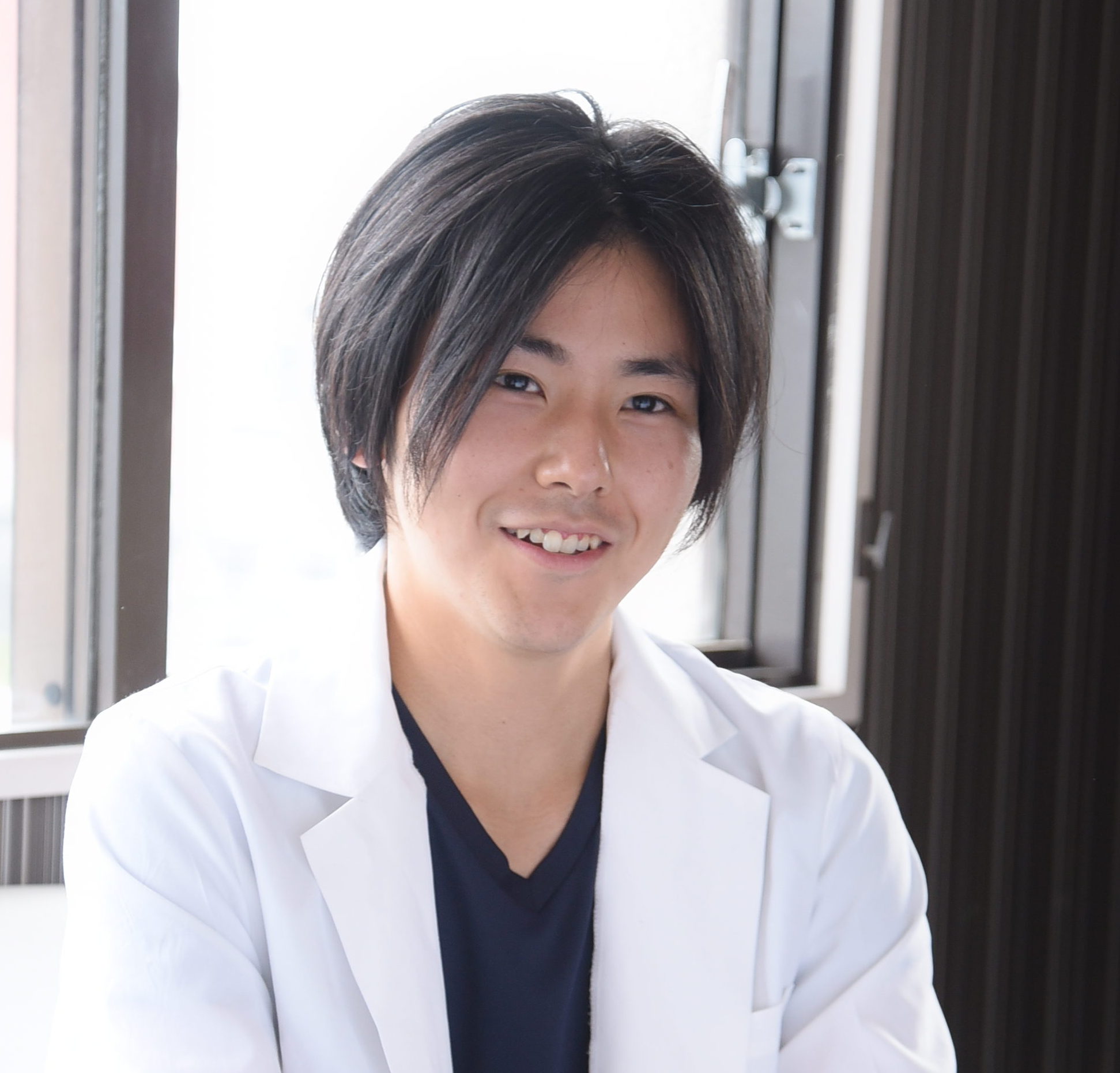
質問ひとつで人生を変えるぐらいの影響を及ぼすこともあるんですよ。
このページでは
- コーチングにおける質問とは
- 一般的な質問とコーチングの質問の違い
- コーチングにおける質問の効果
- より良い質問をおこなうコツ
などを解説していきます。
目次
コーチングの質問と一般的な質問はどこが違うのか

コーチングにおける質問と一般的な質問の違いは質問の目的が違うという点があげられます。
一般的な質問は知的欲求を満たすためにおこなう
一般的な会話における質問は『質問する人が知的欲求を満たす為』におこないます。
例えば
- 『今朝は何を食べましたか?』
- 『週末はどう過ごしましたか?』
- 『趣味はなんですか?』
といった普段の会話で使うような質問は基本的に質問する側の好奇心からくるものです。
コーチングにおける質問は質問された側の自立性を引き出す為におこなう
対するコーチングのおける質問は『質問された側』つまりクライアントの自立性を引き出す為におこないます。
例えばコーチングセッション中にコーチがよく使う質問は
- 今回のセッションではどのような結果を得たいですか?
- 目的を達成する為に今自分がおこなうことは何がありますか?
- 目標に向けて一歩踏み出すとしたらまず何をおこないますか?
といったようなものです。
コーチの質問は基本的にコーチの知的欲求を満たす為におこなうのではありません。
クライアントが目的に向けて主体的に答えを出すことを目的にしています。
コーチングにおいてはクライアントがすでに答えを知っているという基本の考え方があるからです。
コーチングにおける質問の効果とは

コーチングにおける質問の効果は以下の点があげられます。
・クライアントが納得のいく答えを出すことができる
・精神状態の整えることができる
・潜在的な考えに気づくことができる
それぞれ詳しく解説していきます。
自立性、自発性が身に付く
先述したようにコーチングにおける質問にはクライアントの自立性、自発性
を促す意図があります。
ある程度のコーチングセッションを受けて質問を受けることが日常的になってきたクライアントは自分で答えを出し、積極的に行動を起こしていくようになります。
クライアントが納得のいく答えを出すことができる
コーチの質問によってクライアントが出した答えはクライアント自身が納得いくものであるということです。
- 誰かから教えてもらった答え
- 自分で導き出した答え
の2つではたとえ答えの内容が同じだとしてもその後の行動などの質が変わってきます。
なぜなら『誰から教えてもらった答え』はクライアントにとって納得いくものなのか判断材料が欠ける場合があるからです。
対する『自分で導き出した答え』はクライアント自身が質問の内容を吟味し、導き出した答えなので納得のいく結論になります。
精神状態を変えることができる
コーチはクライアントの状態やテーマによってあえて精神状態を変える質問をします。
例えば
- もし求めている結果を達成できたらどのような気持ちを感じますか?
といったようなポジティブな気持ちに促す質問もあれば
- もし、目標に向かって行動を起こさなかったらどのような結果に繋がりますか?
といった不安な気持ちを連想させる質問をおこなったりします。
いずれの質問もクライアントの感情の状態を変えることによって、クライアントをより接触的で責任感の伴った行動へ促すことができます。
潜在的な考えに気づくことができる
コーチは状況によってクライアントが無意識に気づいていない考えに気づかせる為の質問をします。
例えば『年収をあげたい』というクライアントにコーチが
『なぜその結果を得たいと思いますか?』と質問したとします。
するとクライアントは『家族の生活を楽にさせるため』と答えたとします。
この一連のやりとりでクライアントの本当の目的が『年収をあげる』ことではなく、『家族の生活を楽にさせること』ということがわかります。
コーチングにおける質問のコツ

コーチがコーチングセッション中によりよい質問をおこなうコツは以下の点があげられます。
・あらかじめ質問をジャンル分けする
・普段から自分に対して質問(セルフコーチング)する
それぞれ解説していきます。
クライアントの話をよく傾聴し、よく観察する
コーチングセッション中においては、質問の質を左右するのはコーチの傾聴力と観察力です。
- 今クライアントが心から望んでいること
- 今クライアントが抱えている問題や悩みの本質
- 今クライアントが感じている痛みや感情
- クライアントの非言語(体の動きなど)
といった点を傾聴、観察し、総合的に判断したうえで質の良い質問をすることができます。
目の前のクライアントが落ち込んでいるようであれば『気持ちを正常な状態に切り替える質問』をします。
クライアントが問題に対して明確な対処法などが思いつかない場合は『問題に対する視点を変えたり、解決法のヒントに繋がる質問』をします。
こういった『クライアントに適した質問』をおこなうにはコーチの傾聴力や観察力が求められてくるのです。
あらかじめ質問をジャンル分けする
あらかじめ質問をジャンル分けし、覚えておくのもひとつのコツです。
- クライアントの感情を切り替える質問
- クライアントの行動を促す質問
- クライアントの無意識的な考えに気づく質問
といったように最初は『質問のリスト』をつくっているコーチが多いです。
クライアントの悩みやテーマ、状態にあわせてあらかじめストックしておいた質問集から引き出します。
しかし、あまり質問の型ばかり意識してしまうと質問そのものが機械的な印象を受けることがあります。
あくまで質問の目的はクライアントが得たい結果に繋げるためのものです。
質問のバリエーションも大事ですが、いまのクライアントにとって必要な質問を選ぶようにします。
普段から自分に対して質問(セルフコーチング)する
普段から自分に対して質問を投げかけることは質問力を鍛えるうえでとてもおすすめです。
自分に質問を投げかけることによって
- 感情の変化
- 行動の変化
- 生産性の変化
- 問題の対処法
などを客観的、体感的に実感できるからです。
自身が予め体感している質問であれば自信を持ってクライアントに質問を投げかけることが出来ます。












