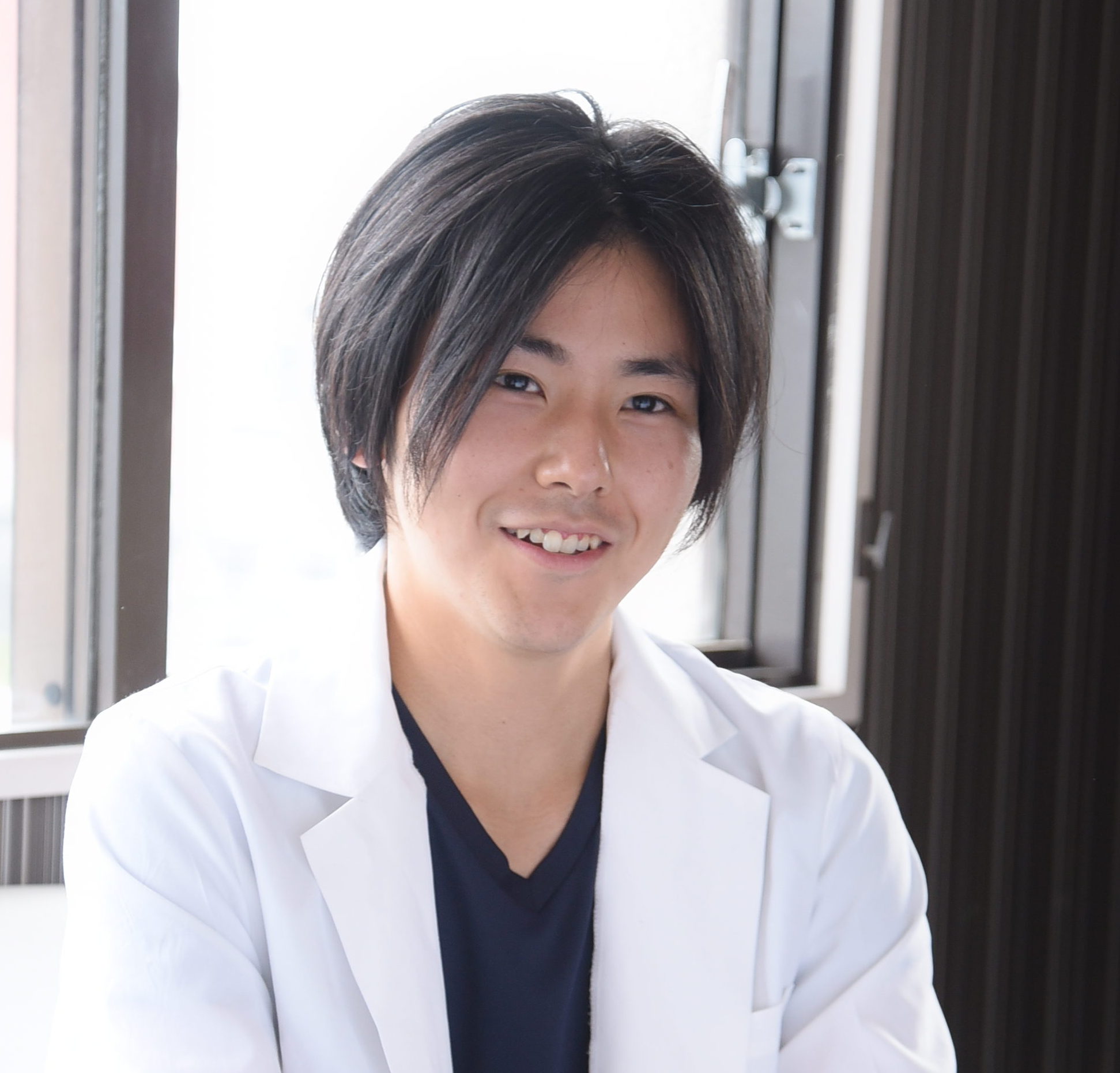本当に自分が嫌になる・・・
生きている上で避けたい感情のひとつが劣等感ではないでしょうか。
劣等感を感じると自信を失ったり、人間関係がギクシャクしてしまったりすることもありますよね。
さらには、相手に敬意を持ちたいのに心の底で妬みを感じてしまうこともあります。
では、『劣等感を感じる原因』はなにか、さらに『劣等感から抜け出す具体的な方法』はあるのでしょうか。
この記事は劣等感で自己嫌悪に陥る人に向けて解決へのヒントを解説していきます。
目次
そもそもなぜ劣等感を感じるのか?

広義的な意味では劣等感は『自分が誰かより劣っていると感じる時の感情』のことを指します。
つまり、『自分が劣っているという主観的な判断』によって人は劣等感を感じるということです。
この、劣等感の引き金となる判断材料は人によって異なります。

例えば、仕事の新卒で企業に就職し、半年が経った状況に自分が置かれているとします。
一定の環境で半年も働けば、職場内で色々な変化があるわけです。
同期入社の同僚と業務成績で差が出来ていたり、、
上司の評価が人によって異なっていたり、、
早い人だとスピード出世している人もいます、、
その変化が起きている状況ひとつひとつをどう受け止めるでしょうか。
例えば、自分と同期入社の社員が成績をあげ、上司に称賛されているというシーンを目撃したときです。
こういうシーンに劣等感を感じやすい人は

といったような解釈をします。
私もよくこのような状況に遭遇し、劣等感を感じていました。
しかし、よくよく考えたら、この考えは非常におかしい話です。
なぜなら、人それぞれ生きてきたバックグラウンドは違うからです。
年齢、性別や出身、性格といったパーソナルなものから
経験や知識といった個々の能力値までもバラバラです。
ただ一つの共通点は『自分と同じタイミングで同じ会社に就職した』という事実だけです。
そういった断片的な状況判断で劣等感を感じるのは非常に非建設的なことなのです。
だからといって、”人それぞれ違うから気にする必要はない”と言い聞かせたところですぐに劣等感が消えるわけではありません。
劣等感をなくすには自分が劣等感を感じるルールを見極める必要があります。
人それぞれ劣等感を感じる基準がある
人が劣等感を感じる裏には自分が無意識的に設定している基準があります。
『自分はこれぐらい出来ていないといけない』という基準です。
例えば先ほどの例の場合、”同期の中で評価される優秀な人”を基準にしたわけです。
この基準の対象が高ければ高いほど、劣等感は強くなります。
例えば、仕事の出来る上司、その会社の社長、その業界の著名人、歴史に残るほどの偉人といったように上をみると果てしなく存在します。
そのなかで、『自分が無意識的に置いている基準はどこなのか』ということに気づくことが劣等感から抜け出す第一歩になります。
問題は視野が狭くなっていること
劣等感そのものは悪いものではなく、向上心を刺激するなど肯定的な効果があります。
問題は特定の部分だけに視野を向けて慢性的に劣等感を感じることです。
慢性的に劣等感で苦しみを感じる人は、ライバルが表彰台にのぼっているシーンばかりを繰り返し見ているような人です。
あの人はあんなことが出来るのか、どうしてあの人はあんなにうまくいくんだとずっと頭の中で会話しています。
それが癖になると、脳は”自分が劣っていると感じる情報”ばかりを探そうとします。
こうなってしまえば、自信や自己肯定感は育ちようがありませんし、自己嫌悪を強める要因になります。
劣等感から脱却するには、この特定のポイントに視点を置く癖から抜け出さなければなりません。
劣等感から抜け出すための3つの方法

劣等感から抜け出すには以下の3つの方法がおすすめです。
・他者評価ではなく、自己評価を基準にする
・自分の実績を紙に書く
それぞれ解説していきます。
比べる対象のバックグラウンドを知る
劣等感を感じるようなことがあったら、まず劣等感を感じる発端となった人のバックグラウンドを知ることです。
結果には必ず原因があります。
自分が劣等感を感じさせる発端となった人は、実は陰で物凄い努力や苦労を重ねてきたのかもしれません。
もしくは、自分より何倍もその分野に関わる経験をしてきたのかもしれません。
大事なことは能力もそうですが『スタート地点は人それぞれ違う』ということに気づくことです。
他者評価ではなく、自己評価を基準にする
劣等感は他者評価より、自己評価を基準にするほど感じにくくなります。
他者評価とは自分以外の誰かが自分に下した評価で、自己評価は自分が自分に対しておこなう評価のことです。
劣等感が強い人ほど他者評価を気にする傾向があります。
上司や先生など目上の評価もさることながら、家族や友人などに少し自信を失くすようなことを言われただけでも劣等感を感じるのです。
また誰かが称賛されていたり、高評価を得ているのを見て劣等感を感じるのも一種の他者評価を気にしていることになります。
その評価は特定の社会や組織が定めている一定の基準でしかありません。
つまり、『自分以外の誰かにとって都合の良い評価』でしかないのです。
自己評価を中心にすると、比べる対象が自分になるので劣等感を感じにくいです。
例えば、自分がそれまで成し遂げてなかった目標にチャレンジするなど評価基準をあげるポイントなど自分で設定することが出来ます。
自分の実績を紙に書く
最後はセラピー的な対処法ですが、自分の実績を紙に書くのも大変効果があります。
白紙の用紙にひたすら自分が人生で成し遂げてきた実績を書いていくのです。
普段、劣等感を感じている人ほどなかなか実績が思い浮かびません。
なぜなら、脳が劣等感を感じることを察知することが癖になっているので、その逆の自分が人より優れているポイントが認識しづらくなっているのです。
このような人は逆に自分が人より劣っていると感じることはスラスラと浮かんできます。
だから、一度この偏った視野を中立的に戻してあげる必要があります。
常日頃自分が自信を感じたこと、人より優れていることなどをこまめに紙に書くように癖づけます。
劣等感が少なくなってくると、自然と自分が優れていると思う点や自信を持てると思う点がスラスラと思い浮かんで紙に書けるようになってきます。