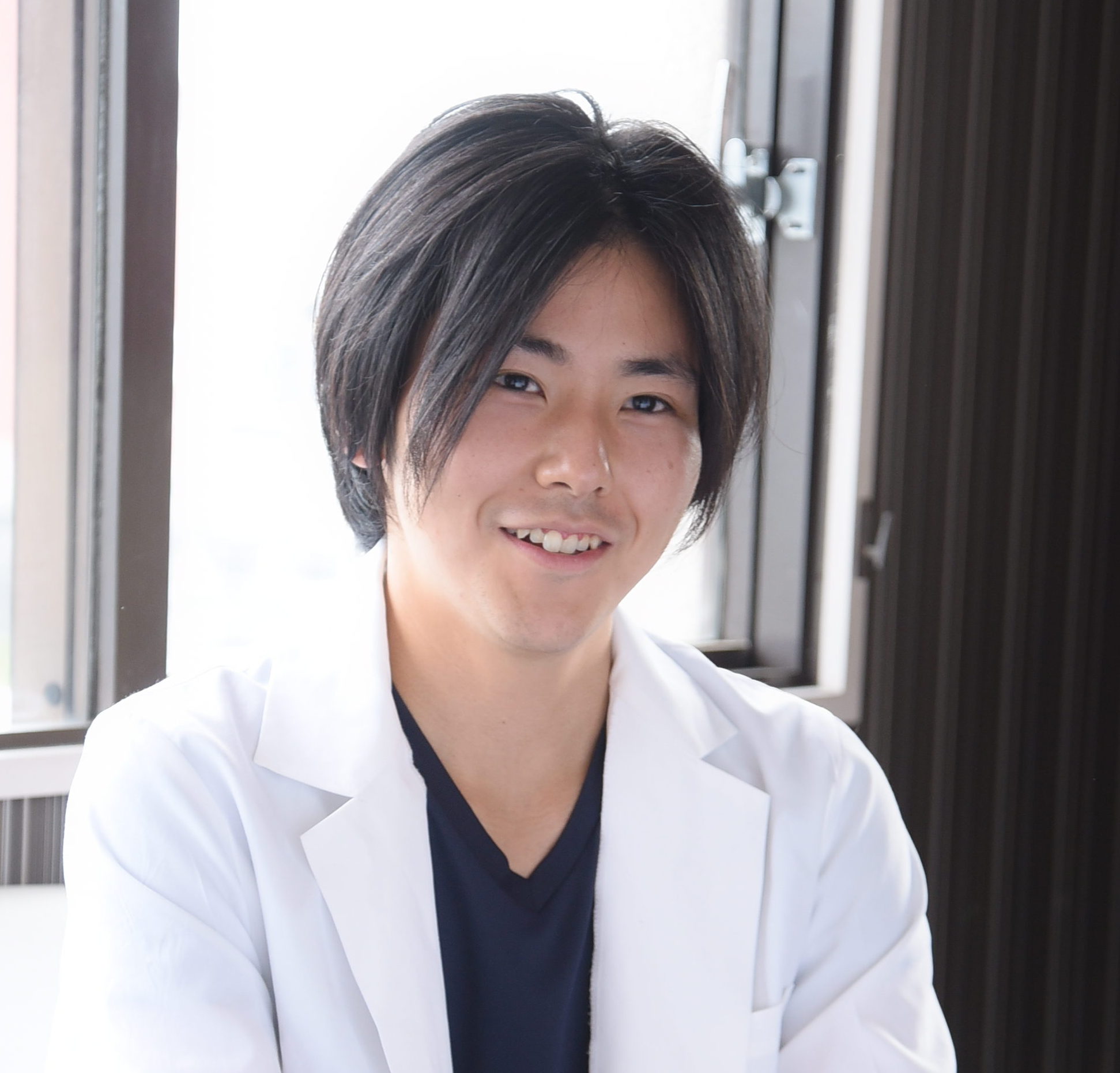結婚は人生の一大イベントとも言われていますがその反面、こころの葛藤があることも多いですよね。

特に結婚を控えた女性にとっては色々想うことが多い時期なのではないのでしょうか。
私と妻は2017年の8月に入籍し、翌月に結婚式を挙げましたが結婚式の準備期間の半年間はお互いにてんてこ舞いだったのをよく覚えています。
そして結婚後によく聞かれたことは『マリッジブルーはありましたか?』という質問です。
あまりにも聞かれたので世の中的にもマリッジブルーは関心の高いテーマなのかもしれませんね。
先に結論を言うと私も妻もマリッジブルーは感じなかったです。
結婚後に聞かれてはじめてそういえばそんな体験なかったなという感じです。
ではなぜ我々はなぜマリッジブルーにならなかったのか?
そしてマリッジブルーになる要因はなんなのか?

コーチとしてもとても気になるテーマだったので体験談を交えて推察してみました。
目次
なぜマリッジブルーになるのか?
そもそもマリッジブルーとはなんぞや?
マリッジブルーの解決策を考える前にまずはマリッジブルーについて定義しておかなければなりません。
マリッジブルーとは、結婚を控えた人が間近に迫った結婚生活に突然不安や憂鬱を覚える、精神的な症状の総称である。
マリッジブルーは漠然とした不安感であり、正確な定義は与えがたい。あえて概要を与えれば以下のようになる。
望んで行う結婚では当事者は喜びに満ち溢れるところだが、結婚に現実のものとして直面すると、結婚後の生活の変化や家庭を持つ責任への不安が突然に強く意識される。
これがマリッジブルーである。マリッジブルーが昂じると、憂鬱から逃れるため最悪の場合婚約の破棄にいたることさえある。
Wikipediaより引用
はっきりとした定義はないそうですがマリッジブルーを一言で表すなら結婚後の環境変化に対する不安を感じる症状全般のようですね。

さらに結婚前だけではなく、結婚してからの数ヶ月間に感じる不安感もマリッジブルーであると定義しているという世論もあるそうです。
ここからは結婚前後の不安や憂鬱をマリッジブルーとして話を進めます。
マリッジブルーになるのは生物として当然の反応
あくまでコーチとしての考察ですがマリッジブルーになるのは極々自然な反応だと思います。
なぜかというと人は無意識的に『変化』に対して抵抗するように設計されているからです。

人を含め、この世のあらゆる生物にはホメオスタシス(恒常性)という機能があります。
ホメオスタシスは一言でいうと自分の秩序や安定を保つ機能です。
結婚に限らず、進学や就職、転職、引っ越し、新しい人間関係など、人生にはあらゆる変化が訪れる時期がありますが、その時におおよその人は大なり小なり、不安を感じたのではないのでしょうか。
ということはそれまでの慣れた環境より、不確定要素がいっぱいの慣れない環境に飛び込もうとしているわけです。
すると無意識はこの何が起きるか分からない環境から身を守るため、悪い出来事を予測して考えてしまうのです。

このことから、不安=変化に対する無意識的な防衛反応と私は定義しています。
なる人とならない人の違いは?
私達がマリッジブルーにならなかった理由
冒頭で私達夫婦はマリッジブルーにならなかったと述べましたがいったいなぜならなかったのでしょうか?
その答えは非常にシンプルで、すでに多くの変化を共有してきたからです。
実際、結婚するまでに付き合っていた2年間のなかで私達は1年間同棲し、2回引っ越しました。
逆に短期間ですが遠距離恋愛になったこともあります。
引っ越しと同時にサロンを開業する時には妻に手伝ってもらいました。
国内、海外問わず、あちこち旅に出かけましたし一緒にセミナーに参加していたりしました。

これがどういうことかというと、多角的にパートナーに対する理解を深めているかということです。
仕事をしている時とプライベートではパートナーの雰囲気や行動パターンも異なりますし、
慣れない環境や問題が起きた時にどう対応するのか、人間関係の付き合い方などその時の状況や環境によってパートナーのさまざまな面を知ることが出来ます。
特に思わぬトラブルや厄介ごと、環境の変化などに二人で対応してきた体験は重要です。
そうなると相手のことはおおよそ知っているので相手とどんな未来を歩むのかが推察ができます。

そうすることでマリッジブルー特有のパートナーに対する不安要素はかなり軽減されるのです。
あくまで結婚は通過点
私達がマリッジブルーにならなかったもうひとつの大きな理由は、結婚後の生活や目標を常に二人で話し合っていたことがあげられます。
ハネムーンの計画を立てることもそうですし、子供をいつ授かるのかとか、家事の分担だとか、親、親戚との付き合いだとかです。
ここまでは一般的にもよく行なっていることだと思いますが、さらに重要なことは二人で話した内容をしっかり書き留めておくことです。
専用のノートを用意するか、できれば部屋の壁面で飾るなどお互いに常日頃目に見えるところに貼って置いておくことがベストです。

ワクワクする計画もその場限りの話で終わらせてしまうとどちらかが忘れて喧嘩のもとになりかねません。
ですから定期的に二人で未来像を話しておくことが良いと私は思います。
付き合いたての頃はそういった話は多くても付き合いを重ねて関係性が安定してしまうと頻度が落ちてしまいがちですからね。
夫婦共通の目標が家族として一体感をもたらします。
ではマリッジブルーになる人はどんな人?
私はマリッジブルーには3つのパターンがあると思っています。
1つはパートナーに対する不安要素が拭えないパターン
もう1つは結婚生活そのものに不安要素があるパターン
そしてもう1つは結婚後の生活に幸せを見出せないパターンです。
パートナーに対する不安要素が拭えないパターン
ひとつめのパターンは前述のとおり、パートナーに対する信頼の欠如からくるものです。
要因として共有した経験が浅かったり、相手の特定の一面しか知らないことがあげられます。
結婚前に同棲をしてなかったカップルなどもこの傾向があると思います。
他にもハネムーン中に旅先でパートナーの知らなかった一面が見え、戸惑いを感じてることがあります。
そして最悪、俗にいう成田離婚までに発生してしまうというのはこれにあたります。

パートナーに対する不安というのはまだパートナーに対する理解が深まり切っていない時に起こるのです。
結婚生活に不安があるパターン
ふたつめは結婚生活そのものに不安があるパターンです。
主婦や夫としてしっかりやっていけるかな、とか引っ越しや同棲に対する環境の変化だとか、相手側の親類との付き合いをうまくやっていけるかなといった不安要素があげられます。
結婚前と結婚後の自分を取り巻く環境に変化があるほどこの反応は大きくなります。
これも前述のとおり、ホメオスタシスによる変化に対する抵抗で心の自然な反応だと私は思います。

ただし、自分の育ってきた家庭環境に影響されているということもあります。
これはどういうことかというと、自分の両親の関係性など夫婦生活に先入観が出来てしまっているという状態です。
極端な話、父親が母親に対して暴力的だったとか片親が健康やお金の管理にだらしなかったとか苦労した体験があると、潜在的に男性に恐怖心があったり、幸せな家庭のイメージが思い描けにくいので否定的な家庭観をもってしまうということもあります。
結婚後の生活に幸せを見出せないパターン
実はこのパターンがいちばん厄介なパターンです。
これがどういうことかというとこのパターンになる人の傾向は
結婚をすることがゴールになっていた人が多いです。
みんなに祝福されながら幸せな結婚式をあげて…
そしてその幸せの絶頂なかハネムーンに行く…
といったようなところに幸せの価値観を置いていたパターンです。
こういったヴィジョンを思い描くのは全く問題ではないです。
しかし、問題は結婚後のヴィジョンや計画を思い描けていないということです。

結婚後の目標やヴィジョンを描けていないまま結婚をしてしまうとどうなるかというと
いわゆるバーンアウト(燃え尽き症候群)になる可能性が高いです。
ハネムーンの終わり頃に生じる憂鬱や虚脱感はこのパターンから生じます。
まとめ
マリッジブルーについての考察はいかがだったでしょうか?
これまでの内容を短くまとめるなら
- マリッジブルーの反応は生物として極自然な反応
- ならない人の傾向はパートナーとの共有経験が多く、夫婦で定期的に将来計画を立てている
- マリッジブルーの原因はパートナーとの関係性、家庭観、ヴィジョンや計画の設定などその人によってパターンが異なる
ということでした。
少しでもヒントになれれば幸いです。
では実際にマリッジブルーになったらどうすれば良いか、
逆にならない為にさらなる対策はなど次回は考察していこうと思います。

![アファメーションの例文をジャンルごとに紹介 [お金.健康.恋愛]](https://takashitamano.com/wp-content/uploads/2020/03/denys-nevozhai-z0nVqfrOqWA-unsplash-150x150.jpg)